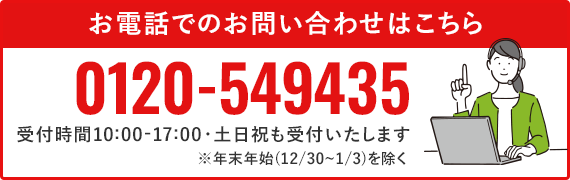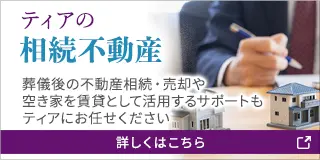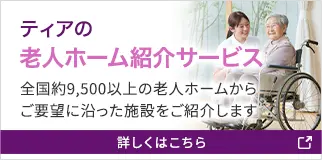相続に関するお役立ち情報
-生前贈与-
【税理士監修】生前贈与とは?相続との違いやメリットを解説

財産を引き継ぐ方法として大きく分けて「相続」と「生前贈与」の2つがあります。
相続対策というと「遺言」を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、生前贈与も有効な方法の一つです。
ただし、生前贈与の内容次第では贈与税や相続税の課税対象になるため、適切な手続きが重要です。
本記事では、生前贈与のメリットや注意点、効果的な活用方法について解説します。
生前贈与とは?
生前贈与とは、生きている間に自分の財産を無償で他人に譲渡することを指します。
一方、相続は自分が亡くなった後に相続人等に財産を引き継ぐことです。
この違いから、生前贈与は「生きている間に財産を渡す方法」として相続とは異なる特徴があります。
生前贈与には年間110万円までの非課税枠があり、この範囲内であれば生前贈与時に贈与税がかかりません。
これを活用することで、財産の早期移転を行うことができます。
贈与と相続の違い
① 合意の有無
贈与 : 双方の合意が必要で、口約束でも成立しますが、贈与契約書を作成することをおすすめします。
相続 : 自分の意思に関係なく発生します。なお、相続人が相続放棄を行う場合は期限があるのでご注意ください。
② 遺言書の必要性
遺言は、財産を誰にどれだけ残すか自分の意思表示を行うものです。
自分の財産につき、どのように相続をさせたいか希望がある場合は、生前に作成が必要です。
③ 財産を渡す相手
贈与 : 贈与契約を行えば家族以外にも財産を渡すことが可能です。
相続 : 遺言があれば相続人のほか、お世話になった人に財産を渡すことが可能です。
④ 基礎控除額の違い
贈与税 : 『年間110万円』が基礎控除額となります。
相続税 : 『3,000万円+600万円×法定相続人の数』が基礎控除額となります。
生前贈与のメリット
メリット① 相続財産の早期移転ができる
自分の意志で家族などに財産の早期移転ができます。
なお、年間110万円までは贈与時の贈与税は非課税となります。
メリット② 贈与時期を選べる
例えば、土地などは価格が上昇する可能性があります。
ただし、贈与後3年以内(2024年以降は7年以内)に相続が発生した場合、その財産は相続財産に加算されます。
そこで上昇する前に贈与を行えば一定の効果が期待できます。
ただし、贈与時に多額の贈与税が発生したり、相続時に「小規模宅地等の特例」が使えることも考えられます。
メリット③ 財産を渡す相手を選べる
生前贈与では希望する相手に自由に財産を渡せます。
相続時に遺留分の問題が発生しても、贈与した財産自体の所有権は受贈者が保持可能です。
メリット④ 相続トラブルを防止できる
相続では親族間の争いが発生することがありますが、生前贈与を活用することでトラブルを未然に防ぐことができます。
贈与契約書の必要性
贈与契約書は、贈与の事実や内容を証明する重要な書類です。
贈与の証明
民法第550条に基づき、書面を残さない贈与は撤回可能とされています。
贈与契約書を作成することで、確実に贈与が行われたことを証明できます。
税務署への対応
贈与契約書がない場合、税務署から贈与を否認されるリスクがあります。
特に暦年贈与を行う場合、書面を残すことが重要です。
名義預金のリスク回避
贈与者が受贈者の同意なく名義だけを変更した場合、それは「名義預金」とみなされ、相続税の課税対象となる可能性があります。
贈与契約書を作成し、双方の合意を明確にすることで、こうしたリスクを回避できます。
まとめ
生前贈与は相続対策として有効な方法ですが、適切な手続きや計画が重要です。
贈与税や相続税の仕組みを理解し、贈与契約書を作成することで、トラブルを防ぎながらスムーズに財産を引き継ぐことができます。
専門家に相談しながら、自分や家族にとって最適な方法を選びましょう。
(記載内容は2025年2月1日までの法改正に基づいています)