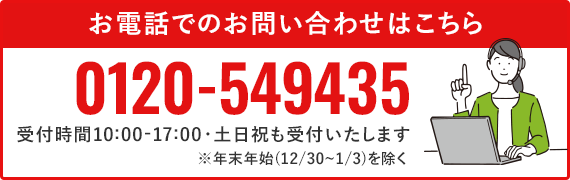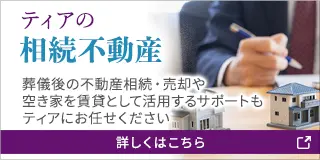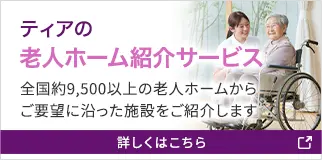相続に関するお役立ち情報
-遺言-
【行政書士監修】遺言書で できることとは?|相続の不安を減らすために知っておきたい基礎知識

「遺言書ってよく聞くけど、実際には何が書けるの?」
そんな疑問を持っている方は少なくありません。
遺言書は、自分が亡くなったあとにどのように財産を引き継ぐかや、家族への想いを残すための大切な手段です。
ただし、書けば必ず実現できるわけではない点に注意が必要です。
法律上効力のない内容もあり、その場合は希望が反映されないまま相続が進んでしまうこともあります。
この記事では、遺言書でできること・できないことを整理しつつ、相続の専門家に相談するメリットもわかりやすくご紹介します。
遺言書に書けること・書けないことの違い
遺言書には、「どの財産を誰に残すか」「家族への想い」などさまざまなことを書くことができますが、法律上の効力がある内容と、そうでない内容があります。
たとえば、「兄弟仲良くしてほしい」といった希望を書くことはできますが、それには法的拘束力はありません。
このような希望は「付言事項」として記しておくことで、遺族の心に響く形で残すことができます。
法的に有効な遺言書にするには?
遺言書の中身が法律で認められた内容であることが重要です。
せっかく書いても、効力がなければ実行されません。
そこで以下に、法律上有効とされる主な項目をまとめました。
法律で認められている「遺言書でできること」
1|財産の処分に関する内容
相続人以外への財産の贈与(遺贈)
親族ではない方や、生前お世話になった方にも財産を渡すことが可能です。
団体や寺院などへの寄付
社会福祉法人・公的機関・宗教法人などへ寄付を行う指定もできます。
信託の設定
財産の一部を信託銀行などに管理・運用してもらうよう設定することも可能です。
2|相続に関する指定
法定相続割合と異なる相続分の指定
遺言によって、各相続人の取り分を自由に決めることができます。
個別財産の受取人を指定
「自宅は長男へ」「預金は次男へ」など、具体的な配分ができます。
一定期間の遺産分割の制限
遺言により、最大5年間は遺産分割を禁止することが可能です。
生前贈与・遺贈の持戻しの免除
生前に渡した贈与財産を、相続時の調整から除外する指定も可能です。
遺留分減殺の方法や順序の指定
遺留分の調整が必要な場合、その手続きの優先順位などを決めておけます。
相続人同士の責任調整
財産に欠陥があった場合の補償責任について、軽減または強化の指定ができます。
遺言執行者の指名
遺言の内容を実際に実行する役割を担う人を指定することができます。
3|家族・身分に関すること
婚外子の認知
法的に認知されることで、その子も相続人として扱われます。
相続人の排除・取消
暴力や重大な侮辱などがあった場合、相続人の権利を排除することができます。
未成年後見人の指名
親権者がいない未成年の子どもがいる場合、後見人を遺言で定めておけます。
遺言書を「残すべき」ケースとは?
遺言書がなくても相続は行われますが、遺言があった方が円滑な相続になるケースは非常に多く見られます。
以下のような方は、早めに遺言書の準備を検討することをおすすめします。
チェックリスト(ひとつでも該当すれば要検討)
子どもがいない
法定相続人がいない
相続人が多数いて話がまとまらない
内縁関係の配偶者がいる
配偶者の今後の生活が不安
相続人の中に行方不明者がいる
介護や世話をしてくれた嫁や婿に報いたい
障がいのある子どもに多く遺したい
家業を引き継ぐ子に集中して財産を渡したい
不動産が資産の大半を占めている
再婚などで家族関係が複雑
認知していない子どもがいる
社会貢献として財産を使ってほしい
自分の意志を相続に反映したい
特定の人物だけに財産を渡したい
すでに子の名義にしている財産がある
専門家に相談する3つのメリット
1. 法的に有効な遺言書が作れる
形式不備や記載ミスで無効になるのを防げます。
2. 相続トラブルの予防
感情的な争いを防ぎ、家族が安心して話し合える状態を作れます。
3. 相続税や不動産なども含めた総合サポート
税理士・司法書士・弁護士などがチームで対応することで、安心感が違います。
相続や遺言のご相談は「ティアの相続サポート」へ
ティアでは、相続に強い専門家(司法書士・行政書士・弁護士など)をご紹介しています。
初回相談無料の事務所も多数。こんなお悩みをお持ちの方は、今すぐご相談ください。
相続の準備をどこから始めたらいいか分からない
遺言書を書きたいけど不安がある
財産が不動産中心で分け方が難しい
相続人同士がうまく話し合えるか心配
よくある質問
Q. 遺言書は自分で書いても大丈夫?
A. 可能ですが、法律に沿った形式でなければ無効になる恐れがあるため、専門家に確認してもらうのがおすすめです。
Q. 遺言書がないと何が問題?
A. 相続人同士で争いが生じたり、法定相続通りに進んでしまい、本人の希望が反映されません。
Q. 生前贈与と遺言書、どちらがいい?
A. 状況によって異なります。税金や将来のトラブルリスクを考慮しながら、専門家と一緒に判断することが大切です。
まとめ
遺言書は、単なる財産分けの指示ではありません。
大切な家族への思いやりを形にし、将来のトラブルを防ぐための備えです。
専門家のサポートを受けながら、納得のいく相続を準備してみませんか?
まずは一度、お気軽にご相談ください。
(記載内容は2025年7月1日までの法改正に基づいています)