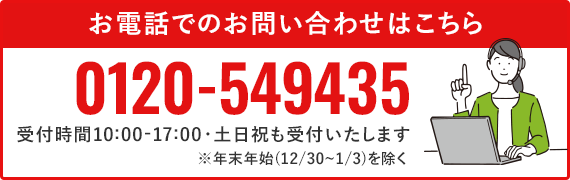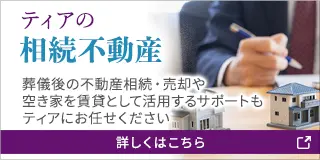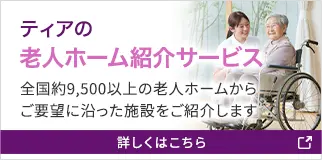相続に関するお役立ち情報
-相続手続きの流れ-
【行政書士監修】最寄りの役場で戸籍が受け取れる? 2024年戸籍法改正で相続手続きがスムーズに!

2024年(令和6年)の戸籍法改正により、被相続人の本籍地に行かずに戸籍を取得できるようになりました(条件を満たす場合に限ります)。
この記事では、戸籍の基本情報や改正内容について解説します。
戸籍とは
戸籍は、日本国民の出生、婚姻、死亡などの法的情報を記録する公的な帳簿です。
家族構成や個人の出生、結婚、離婚、死亡といった重要な事項が記載されており、多くの場面で法的証明として使用されます。
相続で必要な戸籍
相続手続きを進めるには、被相続人(亡くなった方)の「生まれてから亡くなるまで」の戸籍が必要です。
これには、現在有効な戸籍謄本や、過去に閉鎖された除籍謄本・改製原戸籍謄本も含まれます。
これらは、法定相続人(相続する権利を持つ人)を確認し、相続手続きを進めるための重要な資料です。
戸籍謄本(現行戸籍)
現在有効な戸籍で、相続手続きや各種手続きで広く使用される基本的な書類です。
除籍謄本
死亡や婚姻などで戸籍に記載されていた全員が除かれた後、その戸籍自体が「除籍」として閉鎖されます。
除籍謄本は、この閉鎖された戸籍の記録で、相続手続きや過去の家族関係を確認する際に使用されます。
例えば、兄弟姉妹が亡くなった場合や婚姻後に戸籍が分かれた場合などに必要となることがあります。
改製原戸籍謄本
戸籍制度の変更や電算化に伴い、戸籍の形式が変更された際、古い形式の戸籍は「改製原戸籍」として保管されます。
この改製原戸籍謄本は、相続手続きで被相続人の過去の婚姻、離婚、養子縁組などを確認するために使用されることが多いです。
特に、相続人が複数いる場合や過去の家族構成を確認する必要がある際に重要です。
令和6年の戸籍法改正について
令和6年(2024年)施行の戸籍法改正は、国民の利便性向上を目的に行われました。
特に戸籍関連の手続きが柔軟かつ迅速に進められるようになっています。
改正の主なポイントは以下の通りです。
戸籍の取得が最寄りの役場で可能に
従来、戸籍は本籍地の役場でしか取得できませんでしたが、改正により、住んでいる地域の最寄りの市区町村役場でも取得できるようになりました。
本籍地が遠方の場合でも、わざわざ足を運ぶ必要がなくなり、戸籍取得の手間が大幅に軽減されます。
本人確認の強化
最寄りの役場での戸籍取得や電子申請の際、不正取得を防ぐために本人確認手続きが強化されました。マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書が必要で、申請時には厳格な確認が行われます。
相続手続きの円滑化
相続手続きに必要な戸籍を効率的に取得できるようになりました。
これにより、どこの役所でも手続きが可能になり、相続手続きがスムーズに進むことが期待されています。
電子申請の活用も可能なため、特に忙しい相続人にとって大きな利便性の向上が見込まれます。
改正された戸籍法の注意点
● デジタル化されていない(紙ベースで管理されている)戸籍や除籍は、オンラインや最寄りの役場で取得できません。
その場合、被相続人の本籍地の役所で直接請求する必要があります。特に古い戸籍や改製原戸籍が該当することが多いため、遠方の場合は注意が必要です。
● 請求可能な戸籍は、本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母)・直系卑属(子・孫)のものに限られます。
兄弟姉妹の戸籍を請求する場合は、本籍地の役所で手続きが必要です。
● 郵送や代理人による請求は、被相続人の本籍地の役所でのみ可能です。
それ以外の場合は請求者本人が役所に直接行く必要があります。
● 顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)の提示が必要です。
まとめ
令和6年施行の戸籍法改正により、戸籍の取得がこれまでよりも便利になりました。
改正内容を理解することで、相続や戸籍取得に関する手続きをスムーズに進められるだけでなく、必要書類を効率的に揃えられます。
手続きが煩雑な場合や不明点がある場合は、専門家に相談することで安心して進めることができるでしょう。
(記載内容は2025年1月1日までの法改正に基づいています)